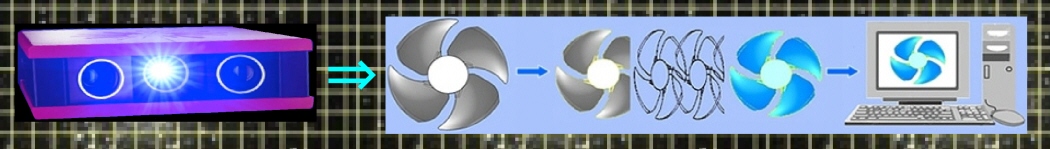鋳造の方法や特徴
- 鋳造の方法:砂型鋳造: この方法では、砂を使って一時的な型を作り、金属を流し込みます。 砂型鋳造は比較的安価で、大きく、部品や一回限りの生産に適しています。永久型鋳造: 金属やセラミックスを使って型を作ります。これは、大量生産に適しており、高品質な鋳造製品が得られます。精密鋳造:複雑な形状の部品を製造するための方法。ワックスや他の材料で原型を作り、その周囲にセラミックの型を作成します。ワックスを溶かして取り除いた後、液体金属を流し込みます。圧力鋳造:金属を型に強制的に流し込む方法。主にアルミニウムや亜鉛合金の製品製造に使用されます。
- 鋳造の特長:
・複雑な形状の部品も製造できます。
・大量生産に適しています。
・材料の無駄が少ない。
・成一体型の部品が製造できるため、組み立ての必要性が軽減されます。 - 鋳造の欠点
・表面仕上げが荒い場合があります。
・材料の特性や製造条件によっては気泡や欠陥が生じる可能性があります。
・精密鋳造などの高度な鋳造方法は、コストが高くなることがあります。
鋳造製品の例としては、エンジンブロック、ギア、パイプ装着、彫像、装飾品などが挙げられます。鋳造は古代からの伝統的な製造技術であり、現代でも多くの産業分野で広く利用されています。
| <トップページへ> |