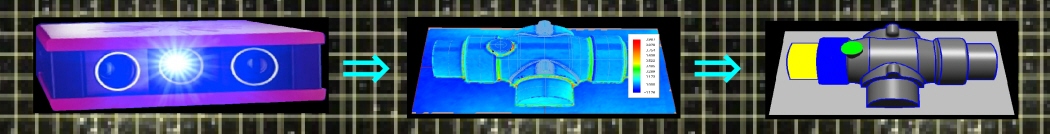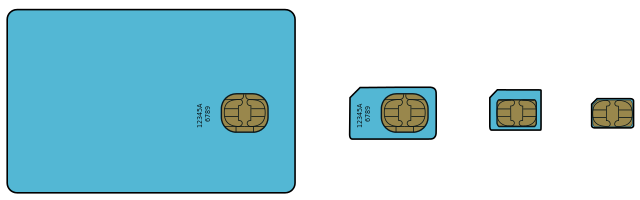筆者はユニクロやRight-Onなどの洋服のお店で服やジーンズの下取り・回収をするサービスを目にしました。
店舗にある回収ボックスに店員さんに回収対象の衣料品か確認してからその対象の衣料を入れるだけです。
サイズ的に穿けなくなったパンツや色あせてしまって着なくなったシャツなどは無料で回収してもらえるのはありがたいです。
特にポリエステル繊維など合成繊維の衣料品などは環境に残るとマイクロプラスチックなどの問題につながりかねません。
いろいろな衣料品の商品を販売する店舗・会社には工夫が必要となっていると言えましょう。
他には、無印良品やユニクロ、Right-Onのお店でカジュアルで動きやすい天然素材の成分100%の衣料品が手に入ります。これも良いことだと考えます。
筆者は小さい頃からアトピー肌でこういった肌にやさしい使いやすい天然素材の成分100%の洋服商品はとてもありがたい存在です。
筆者にとっては季節の変わり目の、季節が変わりきる前に、次の季節に着る洋服を買い物して準備するのも楽しみの一つです。
礼服にも下取りサービスが
先日筆者は祖父の葬式がありました。
そして着ようとしていた洋服の青山で買った以前の黒い礼服がお腹が大きくなってサイズが入らなくなっていることが判明して新しく買いに行きました。
洋服の青山のお店では、礼服購入の時に同じ洋服の青山で買った以前の礼服があれば20000円で下取りをしてくれるサービスがあります。
おかげで新しい黒い礼服を20000円引きの値段で購入することができました。
このような下取り値引きのサービスがあればリピーターが増えるのではないかと考えます。
値段の高いブランド服のオシャレ着もブランドごとにそうしたサービスがあっても良いのではないでしょうか。
生地や洋服の専門家が衣料品の処分やリサイクルなど最終的な場面で活躍していただければまた他にも良いことがありそうです。
購入しやすい値段の洋服などは無料で下取り・回収してくれるだけでも十分ありがたいサービスです。
着まわした後の処分も考えられてしてサービスが充実していて、また新しく購入することなどができれば資源の循環も経済活動もスムーズなリズムになります。