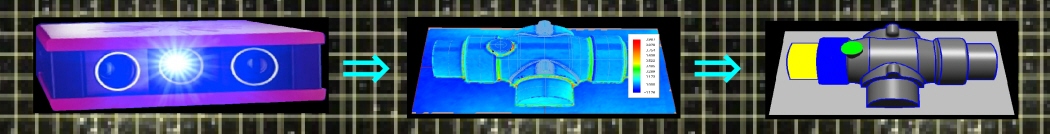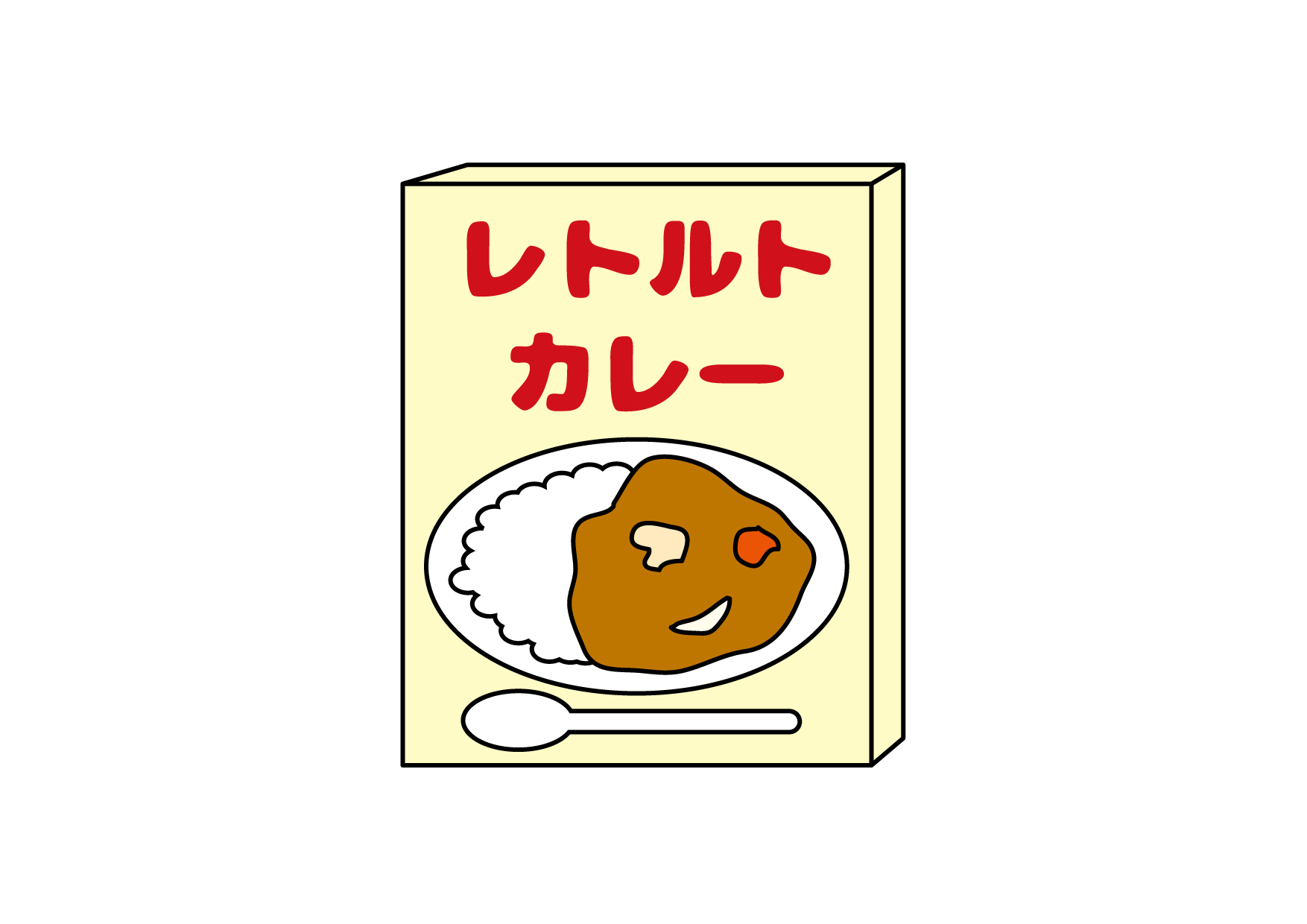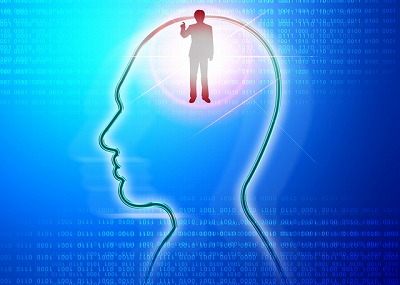2010年から4年間ほど、レジャー農園という農協の五坪の土地を二つ借りて農業をしていました。
父の紹介で会社を引退してから夫婦で農業をしている人を紹介されました。会社を定年で引退してから10年以上夫婦で農業を楽しんでいるそうでした。そこの畑地も農業やってくれとのことでした。最初は私がこきつかわれていたのですが、結局その畑地には母親が農業をしに出かけることになりました。
ですので二人で趣味で農業をすることになりました。
母はガーデニングを10年ほど楽しんでいたので植物は好きだとのことで快諾してくれました。
ちょうど梅雨か梅雨前の時期だとおもいます。
レジャー農園でうれしそうにサトイモにコーヒー豆カスを与えている夫婦を偶然見かけました。
サトイモ栽培にコーヒー豆かすが使えるのかとびっくりしました。
現にその後そのサトイモの苗は大きく成長していました。
そんな時に母の畑地のほうから、喫茶店からコーヒー豆の使った後のカスをもらって土壌に含ませたからそれで農業を頼むとの声がかかりました。
その後その畑地を使っている夫婦によると半分イタズラだったそうです。
コーヒー豆カス入りの土壌にはサトイモが良いよと母に助言をして、その地面でサトイモを栽培してもらいました。大きく育って、美味しいサトイモが見事に育ったそうです。
コーヒーをいれた後のゴミになってしまうコーヒー豆カスがサトイモ栽培に役に立つなんてもったいないしびっくりです。
薬剤師である母はポリフェノールが効いたのではないかと自分で考えていたそうです(詳しくはわかりません)。
ふと見かけた光景からアイデアとなって普通うまく育たないと思われていたイタズラのコーヒー豆カス入りの土壌から見事なサトイモが育ちました。
コーヒーをいれた後のコーヒー豆カスも役に立つようです。
どうせ捨てられるならサトイモ栽培の土壌に生かしてあげたいものです。
もしもカスがゴミ箱行きなら栽培用の土壌にぜひ生かして欲しいです。
おいしかったので大阪の親戚にも贈ってみました。好き嫌いの多い親戚ですがこんな美味いサトイモは食べたことがないと言ったそうです。